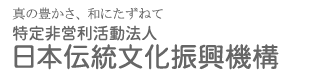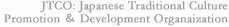江戸前の魚たち その3「浅草海苔」
2017/07/19江戸前の魚たち その3「浅草海苔」

にっぽんおさかな文化あれこれ 第四回
好評をいただいてております「食」に関するコラムシリーズ、第二弾の「魚」!「にっぽんおさかな文化あれこれ 第三回」では江戸におけるシラウオやタイの漁についてご紹介いたしました。第四回は、その他の江戸前の魚や江戸の庶民が食していた魚ついてお話ししてまいります。
浅草海苔
おにぎりやお寿司には欠かせない、おなじみの板海苔。これをときに「浅草海苔」と呼ぶのを聞いたことがありますか?海苔の養殖が始まったのは江戸時代で、そのころから紙状の海苔に加工したものを「浅草海苔」と呼ぶようになったようですが、その発祥については定かではなく、次のような諸説があります。
①江戸時代以前、浅草は海に面していて隅田川河口にあり、美味しい生海苔が獲れていたようですが、その浅草には紙漉きの技術があり、その要領で板海苔へ浅草で加工し浅草寺門前で販売したころから「浅草海苔」と呼ぶようになった。
②大森辺りで獲れた養殖の生海苔を、浅草紙の紙漉き技術のある浅草で加工販売するようになった。
③大森周辺で採取した養殖の生海苔を加工し浅草で販売した。
④これらを併せたような説として、浅草周辺で採れた海苔をそのまま乾かす方法があり、この時に「浅草海苔」と呼ばれ始め、18世紀に入り大森・品川辺りで養殖が始まり「江戸前海苔」・「品川海苔」などとも呼ばれ、最大の養殖・製造を行う生産地となっていった。
このように、「浅草海苔」のいわれは色々とありますが、かつて海苔が江戸の名産品だったことを意外に思われた方も多いのではないでしょうか。筆者は先日、大田区大森にある区の資料館「海苔のふるさと館」に行ってきました。
そこには、国の重要有形文化財に指定されている最後の海苔船「伊藤丸」・海苔採り船「ベカブネ」・乾海苔作りの部屋・道具などが展示されており、また1年間に及ぶ厳しい海苔の生産過程の資料もあり、200年以上続いた「浅草海苔(「江戸前海苔」)」の歴史を知ることができます。
当時の大森周辺の海苔商人には、出稼ぎの信州諏訪出身者が多く、江戸時代後半になると彼らが新たな養殖地を探したり、養殖から製造までの生産技術を大森の生産者とともに全国各地に伝えたりして今に至ります。残念ながら、大森周辺の海苔養殖は東京湾の埋め立てや汚染により昭和37年に漁業権を放棄し、その歴史に幕を閉じました。
最近では、途絶えてしまった「浅草海苔」の「アサクサノリ野生種」という味と香りのよい品種の収穫に成功したようで、昔ながらの「浅草海苔=江戸前海苔」について養殖からの生産を復活させようという動きもでてきたようです。
なお、現在の生産量では佐賀県・兵庫県・福岡県がベストスリーで、東京湾沿岸では千葉県がかろうじて9位となっています。
最後の話題は、江戸庶民が食べていた魚についてです。
江戸前の魚たち その3 「江戸の庶民の魚」につづく
執筆者: 食いしん坊親爺TAKE