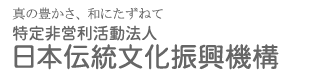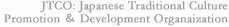江戸前の魚たち その3「江戸前 ウナギ」
2017/07/19江戸前の魚たち その3「江戸前 ウナギ」

にっぽんおさかな文化あれこれ 第四回
好評をいただいてております「食」に関するコラムシリーズ、第二弾の「魚」!「にっぽんおさかな文化あれこれ 第三回」では江戸におけるシラウオやタイの漁についてご紹介いたしました。第四回は、その他の江戸前の魚や江戸の庶民が食していた魚ついてお話ししてまいります。
前回、江戸時代初期に、江戸の人口が急増するに従ってタイとかシラウオ漁が盛んになり、また関西からの漁民の移住もあり、江戸ではいろいろな魚が獲れたはじめたことを書きました。今回は、今まで記述しなかった魚や食材・その流通、江戸前料理などにも触れてみたいと思います。
江戸前 ウナギ
広辞苑でウナギを調べると、「浅草川、深川産の鰻をさす」と書かれているということを、第一回に述べました。
江戸時代に入ってから100年以上経った18世紀前半から中頃にかけて、日比谷辺りの入江の埋め立てやお堀の拡張などが盛んに行われ、浅草川(隅田川の河口付近)・深川(隅田川河口の東側の地名で小名木川他) 辺りで大量に獲れたものが、江戸前=ウナギとなったようです。
ウナギは太平洋のマリアナ海域で孵化し、その後日本の川に戻ってくることが最近わかりましたが、当時の隅田川河口や深川の河口・汽水域は最高の漁場だったのでしょう。現在では、愛知・一色産、静岡・吉田産、鹿児島・川内産・志布志産、宮崎県産の名前が養殖物の産地として有名になっています。ただし、天然ウナギの生産量は養殖の1~2%位しかなく、東京=江戸周辺の産地は、茨城県の利根川・霞ヶ浦と静岡県の浜名湖と狩野川(三島)位になっています。
また、今ではその調理方法で関東風・関西風と分けていますが、もとは1600年代頃、関西で筒切りして焼いていた調理方法から、腹を開いて焼く方法に変わり、それが江戸(関東)に伝わったものです。江戸は武士の都市であることから切腹につながる腹開きを嫌い、背開きに変え白焼き・蒸し・つけ焼きにした蒲焼が誕生、江戸で獲れた美味しいウナギと合わさり江戸前ウナギの蒲焼が定着していったようです。
ということで、現代の江戸前ウナギはその実、江戸=東京で獲れた天然物を関東風に調理した鰻重・鰻丼はほとんど姿を消し、残念ながら他産地の養殖物を使った、調理方法のみ江戸時代から受け継がれた関東風の鰻重・鰻丼に変わってしまいました。
次の話題は、和食とは切っても切れない存在である「海苔」についてです。
江戸前の魚たち その3 「浅草海苔」につづく
執筆者: 食いしん坊親爺TAKE