

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


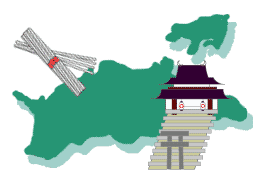 |
主要製造地域:香川県 |
 《特徴》
《特徴》藩政時代、殿さまの奨励と支援を受けた工業や文化は、今日まで永く受け継がれています。香川県では漆器の伝統技法などがその類です。
香川の漆器は歴史の古さよりも、質も量も旧藩の保護と理解のもとに発展し、幾多の名工を生み、巨匠をだしています。
◎象谷塗「ぞうこくぬり」
創始者・玉楮象谷(たまかじ ぞうこく)の名を取り「象谷塗」と呼ばれています。
木地に漆の塗りを繰り返し、最後に池や川辺に自生する真菰(まこも)の粉をまいて仕上げます。
民芸的味わいが深く、使い込むほどに“つや”が出て渋みを増す特徴があります。
◎後藤塗「ごとうぬり」
「梧桐塗」の別名もありますが、創始者・後藤太平翁にちなみ「後藤塗」として広く知られております。
朱を基調にした飽きのこない文様は、使えば使うほど漆のもつ独特の渋さと深い味わいが増すもので、日用品から家具に至るまで塗りの堅牢さと優雅さから広く愛用され、香川の代表格の漆器です。
◎蒟醤 「きんま」
香川漆芸の代表である蒟醤は、タイ国の植物の実の名称だといわれ、何回も塗り重ねた上にケンで文様を線彫りしてそのくぼみに色漆を象嵌する技法で、漆の面を彫るという点では、沈金と変わらないようですが、朱漆、黄漆の色ごとに彫りあげ充填させる作業を繰り返し、全部の充填が終わると表面を平らに研ぎ出すといった独特の技法です。
◎存清 「ぞんせい」
存清の技法は、東南アジアに起こり、中国へ移り、日本へは室町中期に伝えられたとされ、黒地・赤地・黄地などの漆面に色漆で絵を描き、その輪郭部や漆絵の主要部分をケンで線彫りし、細部は毛彫りして仕上げる技法です。
文庫、茶櫃、丸盆など、調度品や生活用品として人気があります。
◎彫漆 「ちょうしつ」
漆を何回も塗り重ねてその表面をケンで彫り、美しい模様を作り出すのが彫漆です。
香川の彫漆の特徴は色漆を塗り重ねて彫るところにあり、例えば、赤漆三十回、緑漆三十回といった具合に塗り重ね、欲しい色層まで表面を彫り下げることにより、埋もれていた漆の色が表れ、芸術性豊かな絵模様が描き出されます。
漆塗りのなかで一番漆の特長が生かされた技法です。
室内インテリアとしても広く親しまれています。
[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定)]
提供 : 香川漆器工業協同組合 様

| 素材 | トチ・ケヤキ・マツ・サクラ・天然漆 |
|---|---|
| 製法・工法 | [象谷塗]
木地磨き>木地固め>刻苧>刻苧研ぎ>磨き>木地固め>磨き>木地固め>磨き>菰付け>菰取り>艶付け>象谷塗仕上げ [後藤塗] 木地磨き(小物の場合)>摺込み>目止め>磨き>摺込み>刻苧>研ぎ>磨き>摺込み>磨き>摺込み>磨き>中塗り>研ぎ>朱中塗り>たたき>柄研ぎ>上塗り>本研ぎ>摺込み>胴摺り>摺込み>胴摺り>摺摺り>後藤塗仕上げ 木地固め(和家具の場合)>刻苧>刻苧研ぎ>布着せ>地付け>地研ぎ>地固め>切粉地付>切粉地研ぎ>切粉地固め>錆付け>錆研ぎ>錆固め>研ぎ>朱中塗り>たたき>柄研ぎ>上塗り>本研ぎ>摺込み>胴摺り>摺込み>胴摺り>摺摺り>後藤塗仕上げ [蒟 醤] 木地固め>刻苧>刻苧研ぎ>布着せ>地付け>地研ぎ>地固め>切粉地付>切粉地研ぎ>切粉地固め>錆付け>錆研ぎ>錆固め>黒中塗り>研ぎ>中塗>研ぎ>上塗り>荒研ぎ>彫り>色埋め>炭研ぎ>呂色研ぎ>摺り>油磨き>摺り>呂色磨き>蒟醤仕上げ [存 清] 木地固め>刻苧>刻苧研ぎ>布着せ>地付け>地研ぎ>地固め>切粉地付>切粉地研ぎ>切粉地固め>錆付け>錆研ぎ>錆固め>黒中塗り>研ぎ>中塗>研ぎ>上塗り>本研ぎ>摺り>呂色磨き>置目>彩色>炭研ぎ>摺り>油磨き>摺リ>呂色磨き>彫入れ>菰付け>存清仕上げ [彫 漆] 木地固め>刻苧>刻苧研ぎ>布着せ>地付け>地研ぎ>地固め>切粉地付>切粉地研ぎ>切粉地固め>錆付け>錆研ぎ>錆固め>色漆塗 A>色中塗 B>色中塗 C>色中塗 D>色中塗 E>上塗り>本研ぎ>彫り>炭研ぎ>呂色研ぎ>摺り>油磨き>摺り>呂色磨き>彫漆仕上げ |
| 歴史 | 古来、香川は芸術的な環境と天分に恵まれていたとはいえ、漆器をこれほどまでに開花させたのはやはり茶や花を愛した殿さまのおかげでしょう。
寛永15年(1638)水戸の国から松平頼重公が高松へ入封、漆器や彫刻をすすめ、名工を育てたが注目されるのは玉楮象谷であります。 玉楮象谷は、文化3年(1806)、高松市の鞘塗師、藤川理右衛門の長男として生まれ、20歳で京都へ遊学しました。 京都では塗師、彫刻師、絵師らと交友を深め、豪放磊落、多彩な才気にみちた象谷翁は、明時代の存清、蒟醤、紅花緑葉など中国伝来の漆塗技法の新しい分野を開拓しました。 象谷翁は、明治2年64歳で亡くなるまで3代の藩主に仕え、今日の漆器の始祖といわれるすばらしい作品を数多く残しています。 市内中央公園には象谷翁の銅像があります。 また、高松藩士、後藤太平は、渋味のある漆塗柄を研究し、下絵についた塵の文様にヒントを得て、のちに“後藤塗”といわれる塗手法を創案しました。 これらの大先輩によって、開発完成された香川の漆器の伝統を継承し、さらに発展の功労者としては、重要無形文化財蒟醤技術保持者になった故磯井如真や故音丸耕堂(重要無形文化財彫漆技術保持者)の活躍など、多くの巨匠を育ててきました。 これらの技法は、漆器組合はむろん香川県立漆芸研究所でも若い人達の育成につとめており、伝統技法の保存と発展に努力しています。 |
| 関連URL | http://www.kagawashikki.org/ |
◆展示場所
香川県漆器工業協同組合
〒761-0101 香川県高松市春日町1595
TEL : 087-841-9820 / FAX : 087-841-9854







