

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


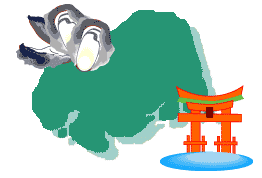 |
主要製造地域:広島県 |
 《特徴》
《特徴》熊野では、毛筆、画筆、化粧筆を生産しています。
毛筆の種類として、特大筆、太筆、中筆、小筆、面相筆や、特殊な筆として、竹や木の筆、もち米の「わら」で作ったわら筆、たんぽぽの種子についている綿毛で作った筆、孔雀や白鳥などの鳥の羽で作った筆などがあります。
また、かたさによって分けると次のようになります。
●羊毛筆(ヤギの毛で作ったやわらかい筆)
●兼毫筆(中間のかたさの筆)
●剛毫筆(かたい毛を使った腰の強い毛)
画筆の種類として、洋画筆、水墨画用筆、日本画用筆、工芸筆などに分けられます。使い方に合わせて大きさや形は様々です。
化粧筆の種類としては、筆を使う顔の場所や、化粧の方法の違いに応じて、様々な大きさと種類に分かれています。
[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定) ]
提供:熊野筆事業協同組合

| 素材 | 馬、タヌキ、イタチ、鹿、ヤギなど |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】毛組
筆の種類によって、必要となる毛の種類は様々です。数多くの毛の中から必要な毛のみを選び、量を決めて組み合わせていく作業です。長年の経験を頼りに、毛の良し悪しを選別していきます。この作業が筆の出来具合を左右するといっても過言ではない、重要な工程です。 【2】火のし・毛もみ 選毛された毛に籾殻(もみがら:米を包んでいるかたい外皮)の灰をまぶし、『火のし』と呼ばれるアイロンをあて、加えた熱の冷めないうちに鹿革に巻いてもみます。毛をまっすぐに伸ばし、油分を抜き取るこの工程は、墨の含みを良くするために大切な作業です。 【3】毛そろえ もんだ毛に櫛をかけて、筆にならない綿毛を取り除いた後、毛の束から少しずつ指先で抜き取り、毛先を積み重ねてそろえます。 【4】さか毛・すれ毛とり 毛そろえした毛のうち、一握りくらいの毛を取り、完全に毛先側にそろえた後、『ハンサシ』と呼ばれる小刀を使って、逆さになっている毛や、毛先がすれてなくなっている毛などを、指先の感覚を頼りに抜き取ります。時間をかけて、筆にならない悪い毛のみを、徹底的に抜き取っていきます。 【5】寸切り 毛を、それぞれの長さに切ります。経済産業大臣指定伝統工芸品の場合、この工程に『寸木』と呼ばれる定規を使って長さを決め、はさみで毛を切ることとされています。 【6】練り混ぜ 寸切りした毛を、薄くのばし、うすい糊を付けながら、何度も折り返してまんべんなく混ぜ合わせていきます。さらに残っている逆毛やすれ毛も取り除きながら、均一になるまで混ぜ合わせる工程です。 【7】芯立て 練り混ぜた毛を適量取り、『コマ』と呼ばれる筒状の型に入れて毛の量を規格の太さに合わせます。この工程でも、不必要な毛をさらに抜き取って、コマから抜き取り、ここでようやく、毛が筆の穂先の形に近づいてきました。これをを乾燥させて出来たものが、筆の穂先の芯の部分となります。 【8】衣毛(上毛)巻き 衣(ころも)毛には、芯になる毛より上質の毛を用います。衣毛は、芯の練り混ぜとほぼ同じ工程をたどって作ったものです。薄く延ばして乾いた芯に巻きつけて、さらに乾燥させます。この工程で芯に巻く衣毛には、穂先を美しく見せる以外にも、芯の短い毛を外に出さないようにするといった役目もあり、筆の書き味を良くするために一役買っています。 【9】糸締め 乾燥させたら根元を麻糸で締めて、焼きごてをあてて少し焼いて、すばやく引き締めます。焼きごてをあてられた毛は溶け、毛のたんぱく質同士がくっつきあって毛が固定されます。この工程で、筆の穂首が完成します。 【10】くり込み 一定の長さの軸を、回転させながら小刀で穂首をはめる部分の厚みを調整し、穂首を接着剤で軸に固定します。 【11】仕上げ 糊を穂首に十分含ませてから櫛でといて毛を整えます。それから、台に固定された糸を穂首に巻きつけ、まわしながら、不要な糊や毛などを取り除きます。形を整え、乾燥させてからキャップをはめます。 【12】銘彫刻 軸の部分に筆の名称などを彫刻する工程です。彫刻の方法は、軸に三角刀をあて、軸のほうを動かして、運筆順の反対のコースをたどって彫っていくやり方です。彫りあがった部分には、顔料を入れて彩色します。 【13】完成 このような工程を経て、1本の筆が出来上がります。 |
| 歴史 | 熊野の筆作りは、江戸時代の末ごろからはじまったと言われています。
当時の熊野の人々は、主に農業でくらしを立てていましたが、農地も少なく、それだけでは生活を支えきれず、農業の暇な時期には、出稼ぎに出ていました。 出稼ぎの帰りには奈良や大阪、有馬(兵庫県)地方で筆や墨を仕入れて、売りながら熊野に帰っていました。これが熊野と筆との結びつきのきっかけとなります。 一方、同じくらいの時期に、井上治平(井上弥助)が、広島藩の筆作りの職人から、また佐々木為次や乙丸常太(音丸常太郎)は、有馬で筆作りを習って帰り、人々に筆作りを広めたと言われています。 |
| 関連URL | http://www.kumanofude.or.jp/ |
◆展示場所
筆の里工房
〒731-4293 広島県安芸郡熊野町中溝5-17-1
TEL:082-855-3010
FAX:082-855-3011
◆イベント開催
「春分の日は 筆の日」
平成20年9月、熊野町で、「筆の日を定める条例」が制定されました。
これは、熊野町制施行90周年の記念すべき年に、「筆の都 熊野町」として、筆産業の振興と筆づくり技術の継承・発展に尽力した先人に感謝するとともに、筆の歴史と文化の価値を改めて認識し、町、事業者及び町民が連携して、その魅力を全国に発信することにより、筆文化の振興と筆産業の発展を図ることを目的としています。
これにより、春分の日と前後3日間の1週間を筆の日週間として、筆のある生活を提案していきます。







