

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


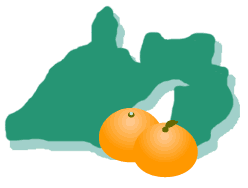 |
主要製造地域:静岡県 |
 《特徴》
《特徴》漆塗、蒔絵という伝統的な技法によって作り出される駿河塗下駄は、なんといっても美しい色彩やユニークなデザインが醸し出す独特の世界が最大の魅力。
静岡の漆器の特色である「木地呂塗」などの各種の変り塗りが応用され、蒔絵の装飾にもさまざまな工夫がなされたことは、「静岡といえば塗下駄」といわれる名声を高めることになった要因です。「蜻蛉塗」「卵殻張り」「八雲塗」「重ね研出」など、バリエーション豊かな変り塗りが多いことも、他の産地にはない特徴です。
戦後、私たちの生活様式が洋風へと変化し、履物の素材自体も化学製品の進出が目覚ましく、下駄そのものの需要が減少しました。
しかし、高級塗下駄産地静岡は、未だ全国首位の位置にあり、伝統を受け継ぎつつも質的な向上を目指し、履物見本市や展示会などに取り組むとともに、浴衣とのコラボレーションをはかるなど、伝統の技術を活かしながら新商品の開発に努めています。
[ 静岡県知事指定郷土工芸品 ]
提供 : 静岡塗下駄工芸組合 様

| 素材 | 日本桐、漆、ウレタン |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】 生地の成形
下駄の原型を作ります。 【2】 木固め 生漆を塗ります。 【3】 布着せ 寒冷紗をのせ、生漆と糊を混ぜたものを塗ります。 【4】 漆の塗り 慎重、丁寧に、漆を塗っていきます。 【5】 研ぎ 駿河炭で表面の細かい凸凹を研ぎます。 【6】 装飾 卵殻の貼り付けていきます。 【7】 磨き 製品を磨き上げます。 【8】 鼻緒付け 鼻緒をつけて完成です。 主な工程を、簡単に説明しましたが、 製作から仕上げまで、45~50工程ほどもあり、手間隙をかけて作られています。 中には仕上げまで、1年以上かかるものもあります。 |
| 歴史 | 静岡におけるはきものの発展には漆器がその裏付けとなっており、特有の技法を応用した塗下駄で全国にその名声を高めてきました。明治初期、下駄職人の本間久治郎は、大衆向けにつくられていた高下駄、吾妻下駄に漆塗りを試みて売り出し、これが静岡での塗下駄の発祥となったと伝えられています。
以来、関東方面での好評に支えられて地方送りも始まり、「静岡といえば塗下駄」といわれるほどの盛況期を迎えることとなりました。 また、静岡の漆器は明治から大正時代にかけて輸出漆器として名をあげたのが、第一次大戦後に輸出が不振になり、このために木地、塗り、蒔絵の職人たちが製造過程の似かよった塗下駄の製造に転換し、それぞれに趣向をこらした製品づくりを競い合ったことが、さらなる発展を促す契機になりました。 |
◆展示場所
駿府楽市
〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町47 アスティ静岡内
TEL : 054-251-1147 / FAX : 054-285-1093







