

総数:401件
- 工芸用具・材料 (1)
- 石工品・貴石細工 (9)
- その他繊維製品 (7)
- 金工品 (21)
- 文具 (14)
- 染色品 (20)
- 漆器 (32)
- 木工品 (44)
- その他工芸品 (76)
- 江戸切子
- 尾張七宝
- 加賀水引細工
- 伊賀組紐
- 播州毛鉤
- 丸亀うちわ
- 甲州手彫印章
- 天童将棋駒
- 房州うちわ
- 姫革細工
- 長崎べっ甲
- 福山琴
- 伊予水引
- 京扇子
- 京うちわ
- 甲州印伝
- 江戸木版画
- 日向はまぐり碁石
- 八女提灯
- 堺五月鯉幟
- 肥前びーどろ
- 矢野かもじ
- きみがらスリッパ
- 三本木ばおり
- 甲州鬼面瓦
- 京くみひも
- 上越クリスタル
- 江戸組紐
- 手描き鯉のぼり
- 和ろうそく
- 菊間瓦
- 大阪三味線
- 京版画
- 草木染手組組紐
- 淀江傘
- のぼり猿
- 油団
- 日永うちわ
- 焼津弓道具
- 日向剣道防具
- 金沢箔
- 結納飾
- 水引工芸
- つる細工
- 日光下駄
- 春日部押絵羽子板
- 津軽凧
- 津軽びいどろ
- 那須の篠工芸
- 琉球ガラス
- 江戸硝子
- 江戸風鈴
- 越谷甲冑
- 伊勢の根付
- 掛川(かけがわ)織
- 見島鬼揚子(おにようず)
- 撫川うちわ
- 棕櫚箒
- 大社の祝凧
- 石見神楽面
- 奈良団扇
- 大門のしめ縄
- 浮世絵手摺木版画
- 越前和蠟燭
- 奈良表具
- 火縄
- 大曲の花火
- 蜻蛉玉
- お六櫛
- 越中福岡の菅笠
- いぶし鬼瓦
- 江戸べっ甲
- 越前水引工芸
- 山鹿灯籠
- 姫てまり
- 三線
- 織物 (50)
- 人形 (29)
- 仏壇・仏具 (12)
- 和紙 (28)
- 竹工品 (10)
- 陶磁器 (48)

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


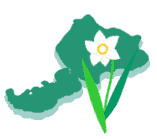 |
主要製造地域:福井県 |
 《特徴》
《特徴》油団とは、和紙を厚く張り合わし油をひいた、夏に用いられる敷物のことです。こげ茶の渋い色をしていて、座るとひんやりと心地よいのが特徴です。
「柱影映りもぞする油団かな」と高浜虚子が俳句に詠んだように、柱の影が映るほどにつるつるとした表面で、俳句の夏の季語にもなっています。
油団は大量の和紙を使用し、多大な手間ひまをかけて製作されます。紙は主に美濃紙や傘紙、提灯紙などを使います。傷んでしまったものは、傷がひどい部分を切り取り少し小さくして使用したり、傷の部分をはぎとって別の油団のはぎれを貼って修復もできます。水気のものをこぼしても、すぐに拭き取ればシミになることはありません。
現在は電化製の冷房機器が多くありますが、便利な道具がない昔は、夏の暑さを凌ぐために活用されていました。油団の表面付近は荏胡麻油が浸透していて隙間がなく、プラスチックのようになっています。中層よりも下層に多く隙間が見られ、この構造によって断熱効果があります。夏の暑い時、上に座っても体温が伝わるので、長時間座ってもプラスチックのようにすぐに温まるのではなく、いつまでもひんやりと涼やかな心地よさを保つことができます。天然素材で作られた油団は、地球にやさしい天然のクーラーとも言えます。
[ 福井県指定無形民俗文化財 ]
情報提供 : 紅屋紅陽堂 様
画像提供 : 鯖江商工会議所経営支援課 様

| 素材 | 和紙、荏胡麻油、渋、柿、糊など |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】 表紙裁断・貼り上げ
和紙を継ぎ貼りします。糊が乾くのを待って油団台(床の上に和紙を袋貼りしたものに柿渋を引いたもの)の上に、紙の表面を下にして約1寸(約30mm)の糊しろで貼り上げます。そこに楮100%の生漉和紙を貼り上げます。 【2】 裏打ち 1分(約3mm)程度の重なりで、6畳の場合6畳分貼り継いだ1枚紙になるよう貼り合せていきます。これを何回か貼り重ねていきます。この段階では、油団を使わないときは表を中にして巻いて蔵などに収めるのですが、その巻く方向に対し紙の目が横目になるようにして、3回貼り重ねます。 【3】 墨打ち 仕上げ寸法に墨つぼを使って線を引きます。 【4】 裏打ち 墨打ちの内側に、5~6匁(1匁 約4g)を、2回目横目の後5~8匁の紙縦目、横目という具合に6回交互に、紙の厚みが 厚い・薄い と交互に貼ります。最後にまた3回横目に貼り重ねます。 最終的に貼り重ねる枚数は13~15枚で、だいたい4mm程度の厚さにします。貼り合せの際は、生麩糊を塗り、しわにならないように貼りつけ、打ち刷毛で叩きます。1層ずつ貼る前に、小刀で紙の中のゴミを削り取ります。 【5】 耳曲げ 充分乾燥した後、油団台から竹へらを使って起こし、墨打ちの外側の部分を1寸3分残し断ち切ります。油団の端の補強のため、この残した部分を裏側へ折り込みしっかり上から押さえます。耳曲げされた部分のはがれを防ぐためと台貼りするために、耳曲げ部分に5分かぶせ、油団の外側に1寸5分ほど出して、油団台に貼り上げを行ったり、場合によっては裏側に1枚紙を貼ったりします。 【6】 渋引き 油団台に貼り上げ、裏に防虫、防腐、ケバ押さえのために柿渋を塗ります。口霧吹き付ける場合と、布に柿渋を浸したもので塗りこむ方法があります。 【7】 耳そぎ 油団台より油団を竹へらで起こし、糊しろ部分を小刀で削ぎ落とします。 【8】 油引き 表に荏胡麻油を塗ります。布に油を含ませ、1回塗った後、すぐに2回目を塗ります。 【9】 天日干し 1日ほど油をよく染み込ませておいてから、その日のうちに油団干し専用の屋根に広げた状態で天日干しします。 【10】 寝かし そのまま1ヶ月ほど、油が紙によく染み込むよう油団を表に向け寝かしておきます。 【11】 艶出し 干し終わると、表面の仕上げをします。つぶした豆腐を木綿の布に包んで、油団の油の表面に刷り込んでいき、その後すぐに乾いた布で磨き込んでいきます。 |
| 歴史 | 油団の起源は定かではありませんが、福井の大安寺地区の、昔 四ヶ村と呼ばれていた地域は、地形的に田地が少なく、大雨の時は冠水のため米の収穫がおぼつかない時もあり、住民の生活は苦しいものでした。
このような厳しい状況の中、大道和尚は少しでも生活を補う手段として手漉き紙を作ることを推奨しました。 幸いこの土地は山を背景にしていくつも谷川や湧き水があり、豊富できれいな水は紙づくりに適しており、四ヶ村ではこの和紙を使った油団づくりが盛んであったと伝えられています。 昭和30~40年頃は、景気がよく注文が多く、福井の表具屋は100店舗以上、油団を作っていた店舗も多くあったと言われています。 電化製品等の普及や、製作に大変手間がかかるため(6畳を毎日3人で作業しても、1ヶ月はかかります) 今現在、油団を作っている店舗は1店舗のみとなりましたが、伝統の技を絶やさないよう受け継いでいます。 |
◆展示場所
紅屋紅陽堂
〒916-0087 福井県鯖江市田村町2-10
TEL : 0778-62-1126







