

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


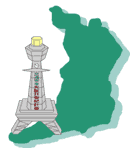 |
主要製造地域:大阪府 |
 《特徴》
《特徴》緞通(だんつう)は、中近東から中国を経て日本に伝来し、江戸時代から近代にかけて盛んに生産された手織りの敷物のことです。兵庫県の旧赤穂藩、佐賀県の旧鍋島藩と並んで日本三大緞通と呼ばれる堺緞通は、垂直になった織機で織り上げます。
出来上がった作品は緻密で美しいデザインと、深い風合いを兼ね備えていることが特徴です。また、赤穂・鍋島が主に国内向けに生産されていたのに対し、堺緞通は海外に多く輸出されていました。
堺緞通の最後の名人と呼ばれる辻林白峰氏(本名:辻林峯太郎)は、家業として緞通製造にかかわりながら、文様を絵画的に表現する技法を磨き上げ、その生涯を堺緞通の伝承にささげました。作品には、堺の風物を表現したものが多く残されています。
[ 大阪府指定無形民俗文化財 ]
提供 : 堺式手織緞通技術保存協会 様

| 素材 | 木綿や絹糸、羊毛など |
|---|---|
| 製法・工法 | 堺緞通は、堺の藤本庄左衛門という人が、中国緞通や九州鍋島緞通などのよいところを取り、天保2年に堺緞通と名づけ売り出したのが始めとされています。当時は交通が開けておらず、大阪や京都への販売が主で、質もあまりよいものではなかったとされています。
明治になり、西洋文化が入ってきて、染めや織りの知識が発達しました。藤本庄左衛門の孫にあたる荘太郎が、苦心を重ね織り方を改良し、大きなものが織れるようになります。模様や色も改善され、堺緞通の質は大きく向上し、やがてアメリカ、フランス、イギリスやドイツなどへ輸出されるようになりました。 さらに絹糸や羊毛、毛糸、牛毛の緞通、麻緞通なども作られるようになりました。中でも麻緞通は、外国から輸入した米袋などの廃物の糸を原料としたもので、販売価格が安く、9割近くが海外へ輸出されていました。麻緞通はかたい麻を扱うため、手が荒れ糸に血がにじむほど苦労が多かったと言われています。 明治26年にはアメリカのシカゴ博覧会に出品され、藤本荘太郎自身も渡米し堺緞通を広め、販路を拡大、明治28年には輸出のピークを迎えます。堺はさながら「緞通都市」の様を呈し、荘太郎は「緞通王」と呼ばれていたといいます。 |
| 歴史 | 【1】 染色・合糸
パイル糸(編みこみ用の糸)は、かつて木綿・麻・絹が使われていましたが、現在はほとんどが羊毛です。 【2】 整糸 経糸の本数、長さを整えて織機のかけます。 【3】 図案 専用の方眼紙(和紙)に全図または1/4図を書きます。 【4】 織り パイル糸は紡毛糸を6本引きそろえて用い、図案の色の配色に従って、1本ずつ指先で経糸2本に結びつけます。1本結びつけるごとに逆手に握った手鋏で糸を切り、筬で打ちつけます。緯糸は綿糸(ガラ紡糸・再生糸)で1段ごとにゆるく手で入れ、筬で打ちます。 【5】 糊付け・乾燥 織り上がった緞通を板の上に釘で固定し、裏面で刷毛で糊を全体に塗り、ひなたで乾燥させます。 【6】 剪毛・仕上げ パイル面をシャーリング(バリカン)できれいに整えます。縁は三つ折にして糸で縫いつけて仕上げます。 |
◆展示場所
下記施設にて、堺緞通の見学及び毎週月曜は制作実演の見学が可能です。
◎堺伝統産業会館
〒590-0941 堺市堺区材木町西一丁1-30
TEL : 072-227-1001 / FAX : 072-227-5006
◎堺市産業振興センター
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町183番地5
TEL : 072-255-3311 : FAX 072-255-5200







