

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


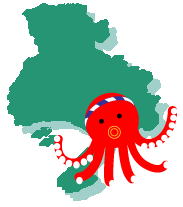 |
主要製造地域:兵庫県 |
 《特徴》
《特徴》日本国内で和紙の原料となる主要な植物には、
楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)がある。雁皮はジンチョウゲ科の落葉低木で、東は静岡県伊豆、北は石川県加賀市付近を境にその西南地域の山間地に自生する。生育が遅く、また栽培が難しいため栽培原料としては採算性がひくく、現在も野生のものを採集し原料としている。
その繊維は平滑で半透明、しかも粘性に富み、雁皮のみで抄造された紙は独特の光沢をもち、平滑でつやのある高級和紙として珍重される。
また、楮の利用は中国にその起源もつが、雁皮は日本独自のものである。
特に名塩紙は、日本のほかの地方に例を見ない溜漉きという最も古い抄紙形態を伝えている点で注目される。
現在では、原料に雁皮を混合する生産地は多いが、生漉きの雁皮紙を生業として生産する紙郷は限定される。
西宮市名塩では、江戸時代はじめにはすでに製紙業を開始しており、その当初から雁皮のみを原料としており、現在も変わらない。
抄紙に際しては、男性が舟(漉草を入れ作業をする松材でできた大箱)の前に趺座し、「溜漉法」によって漉草を汲む。また、原料の雁皮に地元産の泥土の微粒子を漉き込む。
雁皮の特長と泥土が相俟って、日に焼けず虫のつかない独自の紙を生み、屏風・襖用の「間似合紙」や、金銀箔を打つ際に重要な「箔打原紙」という独特の需要を担ってきた。
このように、名塩紙は、我国紙料の代表である雁皮を利用した抄紙業として伝統を堅持する、きわめて数少ない紙として、重要無形文化財に指定された。
[ 国指定重要無形文化財 ]
提供 : 西宮観光協会 様、西宮市立郷土資料館 様

| 素材 | 雁皮および地元産の泥土 |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】 雁皮の処理
はぎとった雁皮の皮から表面の黒い皮をていねいに取り除く。残った白い皮をうすく短くはぎとる。 【2】 灰じるで煮る 水と灰じる(またはソーダ灰)を入れた釜で、黒皮を取った雁皮を煮る。6時間ほど煮ると、手でちぎることができるくらいやわらかくなる。 【3】 さらに白く 煮た雁皮をきれいな水で洗い、時間をかけてチリやゴミを取り除く。 【4】 雁皮をほぐす 白くやわらかくなった雁皮をたたいてほぐす。 【5】 泥土をつくる 名塩の山の土を細かくして、地面に作った穴に入れ、土こねぼうで土の粒が見えなくなるまですりつぶす。こうして細かい土を含んだ水が出来上がる。 名塩の紙に使われる土は4色あり、紙の種類によって使い分ける。 【6】 シャナをつくる シャナとは、ノリウツギという植物の皮を発酵させ、その汁をしぼり出して作るネリのこと。シャナには雁皮が一枚の紙になるのを助ける作用があり、紙すきの際に使用する。 【7】 しかけ 木でできたすき舟の中に、やわらかくなった雁皮や水、次に水にといた土をいれ、カイカイと呼ばれる道具でしっかり混ぜる。 【8】 紙をすく すき舟にシャナを入れ、竹の棒でよくかきまわす。簀をはさんだ簀桁を両手で持ち、混じりあった原料をくみあげ、簀桁をゆっくりゆすりながら水をおとす。これを5~6回繰り返す。 【9】 水を切る すき上がった紙はしばらく水を切り、積板の上に重ねていく。100枚ほどたまると、重石を2時間に1つずつ計8個ほど乗せ、できたばかりの紙がいたまないよう、水をしぼり出す。 【10】 紙を乾かす 水を切り終わったら、イチョウなどで作った干板に、はけを使ってはきつけて、日に干して乾燥させる。板に張り付いた面が表面になる。 【11】 しあげ 乾いた紙を干板からはがし、端をそろえる。 |
| 歴史 | 雁皮を紙料とする紙は、古代には「斐紙」(ひし)と呼ばれ、下っては「鳥子紙」(とりのこし)や雁皮紙(がんぴし)と呼称された。
原料の入手が比較的容易であった楮等を用いた紙がひろく普及したのにくらべ、雁皮紙はその利用が特定され、高級紙として使用されることが多かった。 旧名塩村(現西宮市塩瀬町名塩)には、江戸時代初期に、雁皮製紙「鳥の子」の先進地越前の技術が導入されたといわれている。 そして名塩において、地元から産する各種の色相をもつ泥土の微粒子を混ぜることによって、越前にはない新しい技術が開発されたのである。 江戸時代には藩札の需要も多かったが、現在、名塩鳥の子紙は書画、美術用、箔打紙は金箔圧延用、間似合紙は襖用に特注を受けている。 |
◆展示場所
西宮市立郷土資料館分館 名塩和紙学習館
〒699-1147 兵庫県西宮市名塩2丁目10-8
TEL : 0797-61-0880 / FAX : 0797-61-0891
開館時間 : 9:00~17:00 (入館16:00まで)
休館日 : 月曜日、年末年始(12/29~1/4)※臨時休館あり
◆イベント開催
西宮市立郷土資料館分館 名塩和紙学習館
団体様向けに紙漉き実習を行っております。







