

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


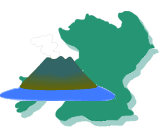 |
主要製造地域:熊本県 |
 《特徴》
《特徴》高浜焼の材料となる、熊本県の天草下島では17世紀に発見された「天草陶石」が採掘されます。
江戸時代に平賀源内によって「天下無双の土」と絶賛されたこの陶石は、現在でも国内最高品質の白磁原料として知られ、有田や瀬戸などの高級磁器の原料として利用されています。
白く透明感があり硬質な天草陶石はこのように多くの磁器原料として有名なだけではなく、古くから高浜の上田家代々によって「高浜焼」として独特な磁器文化を生み出してきました。
[ 熊本県指定伝統的工芸品 ]
提供 : 上田陶石合資会社 様

| 素材 | 天草陶石(天草陶土) |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】 天草陶土
高浜焼の材料となる天草陶土を採掘します。 【2】 成形 成形にはロクロ、石こう型を使用します。 【3】 仕上と乾燥 成形されたものを仕上げます。その後、よく乾燥させます。 【4】 素焼 ガス窯にて約900℃で焼成します。 【5】 下絵付と施秞 ゴスを使用して、下絵を描写します。下絵づけが終わったら、浸掛にて上秞をかけます。 【6】 窯詰と本焼き 本焼窯にて棚組みをします。その後、ガス窯にて1,300℃で本焼焼成します。 【7】 上絵と完成 絵を手描きまたは転写し、電気炉にて750~800℃で焼成し、完成となります。 |
| 歴史 | 【天草陶石の発見】
天草陶石が発見されたのは、かなり古く元禄年間に旧高浜村皿山及び旧下津深江村で採掘されていたと伝えられていますが、定かではありません。 正徳2(1712)年頃、肥前の製陶業者に天草陶石を供給したのが、製陶原料として使用した始めとされています。明和8(1771)年には平賀源内が長崎奉行に提出した『陶器工夫書』で「天下無双の上品」と賞賛しました。 【高浜焼のはじまり】 上田家代々の累記を見ると、高浜村上田家の祖、第3代伝右衛門が享保13(1728)年に採掘し享保15年に中止しています。 その後第5代勘右衛門達賢が宝暦4(1754)年に採掘を再開しており、当時は砥石または硯石として出荷されていました。 第6代目伝五右衛門武弼は、天草陶石が陶磁器原料として最も優良であること聞き、肥前長与の陶工山道喜右衛門を招き、宝暦12(1762)年に高浜村鷹の巣山で焼物を焼き始めました。これが高浜焼の元祖とわれています。 元来、天草はいたるところの山岳が起伏して平野に乏しく、田畑が少なかったため、村民は農耕をすることにも非常に困難でした。 伝五右衛門武弼は深くこれを憂い、土地の民に新しい産業を与えようと種々研究し、陶石を利用することを考え、多大の経費をかけましたが利益は出ませんでした。 そこでしばしば陶業を止めようとしましたが、土地の民が失業し、生活が困窮することを考えるとどうしても廃業できませんでした。 欠損を省みずに事業を継続して、ついに鷹の巣山一郷数百人の生業とすることができたのです。 |
| 関連URL | http://takahamayaki.jp/ |
◆展示場所
◎上田資料館
〒863-2804 熊本県天草市天草町高浜南598
TEL : 0969-42-1115
開園時間 : 9:00~17:00
定休日 : 年末年始(12月31日~1月3日)、盆(8月14~15日)
◎寿芳窯 売店
〒863-2804 熊本県天草市天草町高浜南598
TEL : 0969-42-1115
営業時間 : 8:00~17:00(平日)、8:30~17:00(土日祝)
定休日 : 年末年始(12月31日~1月3日)、盆(8月14~15日)







