

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


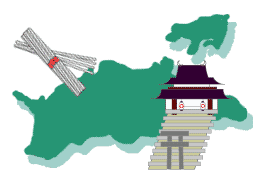 |
主要製造地域:香川県 |
 《特徴》
《特徴》和紙による手描き鯉のぼりは、ナイロンプリント印刷による鯉のぼりが主流になっている現在、需要は多くなく、また、大量生産もできません。
また、印刷のような完璧な鯉のぼりを鯉のぼりに求める人にも受け入れられないものであります。
しかし、同じものが一つとしてない、手描きに価値を認め、その独特のぬくもりを感じ取っていただける人に支えられています。
[ 香川県指定伝統的工芸品 ]
提供 : 手描き鯉のぼり・三池 様

| 素材 | 和紙 |
|---|---|
| 製法・工法 | 【1】 紙合わせ
和紙を継ぎ合わせた後、それを2枚ずつ合わせて重ねます。和紙には、裏表がありそれを考慮しながら行います。 その後、型取りし合わせた紙に型紙をあてて、型取りをしていきます。 【2】 断裁 刃物で型取りに沿って断裁していきます。もちろん、裁断作業も手作業です。 【3】 貼り合わせ 縁取りしたところへ紙紐を入れて(サイズの大きな鯉のみ)、上下の紙を貼り合わせます。紙紐を入れるのは、継ぎ目を強くするためです。 【4】 目入れ 次に、目入れをします。 大きなサイズの鯉のぼりの場合は目玉を型どった各サイズの版を押していきます。目玉の版を押した場合、黒く縁取られた後、黒目のまわりをブルーやピンクなどで、色どっていきます。 小さなサイズの鯉のぼりは、紙製の目玉のシールを貼っていきます。 【5】 金太郎入れ 続いて、鯉のぼりに金太郎を描いていく「金太郎(金時)入れ」は、金太郎(金時)の型紙で魚体中央に型を入れた後、赤と黒で描く。これは、真鯉のみに限られています。 鯉のサイズや、地方によっては入れない場合があります。 【4】 荒がき ウロコ、エラ、ヒレなどを手描きで入れていきます。 これは、かなり熟練を要する作業となります。まるで機械で書いているように、正確に素早く描いていきます。 【5】 ぼかし 線だけの荒がきに沿って濃淡2色で縁取っていきます。 大きな鯉の場合、2つの壷に濃淡2色の染料が入っていて、1つのハケの両端にそれぞれ濃淡の染料を同時に含ませて描いていきます。 “塗り”と呼ばれる作業は、“荒がき”と“ぼかし”の空間を塗り尽くし、金太郎に彩色し、エラ、ヒレ、尾などに黄を入れます。 【6】 金箔付け 金箔付けは、ウロコに金箔の型を押します。 大きな鯉の場合は、シルクスクリーンを用います。 小さな鯉の場合は、はんこのようなものに金箔を付けて版を押します。 【7】 口張り 口に輪をはめて完成です。口輪の材料は、竹や針金が使われています。 |
| 歴史 | 豪快な筆使いと、独特のぼかしが特徴の手描き鯉のぼりは、昭和30年頃から40年にかけて盛んに作られました。
それ以降は現在あるナイロンプリント印刷が主流になりました。 出荷地域は主に、西日本一円で、最盛期には、海外にも輸出され、昭和61年に香川県の伝統的工芸品に指定されました。 |
◆展示場所
JR坂出駅
香川県坂出市。瀬戸大橋を渡って最初の駅。
〒762-0045 香川県坂出市元町1丁目1-1







