

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


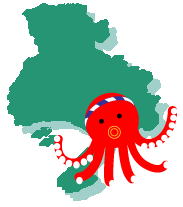 |
主要製造地域:兵庫県 |
 《特徴》
《特徴》姫路は、今なお美しい姿を留める白鷺城(姫路城)を中心に城下町として、また、播州地方では姫革製品(牛革を白くなめした革)の特産地として栄えてきました。
姫路だけで生産される姫革は、漂白・染色せずともなめしたままで輝くように白く、日光に当たるとさらに白さが増すという特徴を持っています。
姫革細工は、この革に型押しと手描きで華やかな文様を施し、財布やバッグなどの小物に仕立てたものです。
しっとりと手になじみ、軽くて丈夫な姫革細工は、長年に渡ってご愛用いただけます。
[兵庫県指定伝統的工芸品]
提供 : 有限会社キャッスルレザー 様
◆伝統工芸品通販 和遊苑
姫革細工の小物を多数お取扱いしております。ぜひご覧くださいませ。


| 素材 | 牛革 |
|---|---|
| 製法・工法 | 生地作りが、この細工の特長(伝統の技)で、縫製まで5工程に別かれます。
【1】 荒裁ち 型紙を使い、やや大きめに印しし、革を裁断をする。「姫革細工」の最初の工程です。 革のクセを考えながら、型紙を使い鉛筆で印します。 大きめに裁断をするのは、後の工程で縮むからです。 【2】 シボ出し 革にシボと呼ばれるシワを作ります。 シボ出しで、揉む事で革本来の持つ、シボが出来ます。 シボとは、革のシワです。 【3】 型押し 様々な絵柄が有り型を入れる事で、立体感が出ます。 革に型を押すので絵に立体感が出、また、手にフィットします。 様々な絵柄が有り、商品をイメージし型を押します。 昔は木型を使用してましたが、現在は、金型を使っています。 【4】 色塗り 筆で顔料を塗ります。 ボカシ・二度塗り・ベタ塗りと独特な塗りかたをします。 天候によりますが、12時間~20時間で乾きます。 大きさや絵柄にも、よりますが1日に塗る量ががぎられます。 【5】 サビ入れ サビと呼ばれる物を刷り込み、仕上げニスを塗ります。 サビ(漆・顔料)を刷り込む事で絵柄やシボを浮立たせる。仕上げニスを塗ると、表面保護・防水・汚れにくく成ります。 サビ入れは、自然乾燥なので温度や湿度に気を使います。 【6】 縫製 生地が出来上がると、本裁ちをし、「縫製」をする。幾日もかかった生地が出来上がると、本裁ち(裁断)をします。 絵柄を生かした、又、革の特徴を生かした縫製をしています。 姫革は、とても軽いので、最近は、袋物も手掛けています。 生地作りは、天候が良ければ4日間で仕上がります。 |
| 歴史 | 白鞣の歴史は古く、四・五世紀頃にはすでに作られていました。
戦国時代・安土桃山時代には、豊臣秀吉の派手好きな性格が反映したのでしょうか、軽くて、強靭で、しなやかな皮革は武将の鎧冑や馬具に用いられてきました。 鮮やかな装飾性豊かな武具を作りだした技術技法は受け継がれ平穏な江戸時代をむかえると、煙草入れ・文庫などの細工物を作りだすように なりました。 今では、バック・財布などの日常品、文庫・テーブルセンターなどの装飾品と伝統的革細工物として珍重されています。 |
| 関連URL | http://www.castle7.com/ |
◆展示場所
◎オンライン販売
伝統工芸 和雑貨ショップ 和遊苑
JTCOが委託運営するオンラインショップです。どこよりも幅広い商品ラインと、色柄をご紹介しております。ぜひお立ち寄りください。
伝統工芸品通販 和遊苑 姫革細工








