

総数:401件

総数:401件
- 北海道 (3)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (6)
- 宮城県 (7)
- 秋田県 (9)
- 山形県 (11)
- 福島県 (13)
- 茨城県 (6)
- 栃木県 (8)
- 群馬県 (6)
- 埼玉県 (11)
- 千葉県 (6)
- 東京都 (14)
- 神奈川県 (5)
- 新潟県 (10)
- 富山県 (10)
- 石川県 (12)
- 福井県 (12)
- 山梨県 (7)
- 長野県 (7)
- 岐阜県 (10)
- 静岡県 (9)
- 愛知県 (14)
- 三重県 (14)
- 滋賀県 (9)
- 京都府 (17)
- 大阪府 (10)
- 兵庫県 (11)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (6)
- 鳥取県 (6)
- 島根県 (11)
- 岡山県 (6)
- 広島県 (8)
- 山口県 (5)
- 徳島県 (4)
- 香川県 (7)
- 愛媛県 (9)
- 高知県 (5)
- 福岡県 (12)
- 佐賀県 (7)
- 長崎県 (6)
- 熊本県 (9)
- 大分県 (2)
- 宮崎県 (8)
- 鹿児島県 (7)
- 沖縄県 (8)


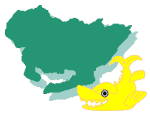 |
主要製造地域:愛知県 |
 《特徴》
《特徴》猿投山麓の静かな風土に育まれて、一千年を超える赤津焼は、日本六古窯の一つに数えられ、良質の陶土、赤津地域のみに産出する原料にめぐまれて、すぐれた陶工が生まれ、育ち、その技術や、技法が今日まで受けつがれ、美術工芸品、茶華道用具、一般食卓用品に、脈々と息づいています。
[ 国指定伝統的工芸品(経済産業大臣指定) ]
提供:赤津焼工業協同組合 様

| 素材 | 灰・鉄・石 など |
|---|---|
| 製法・工法 | 伝統工芸品である赤津焼の釉薬には7種類があります。
【灰釉】 平安時代前期、食器等に使われた灰の溶釉、自然釉 【黄瀬戸】 鉄釉の一種で鉄分の含有率は10%程度で美しい黄色に発色する。桃山時代茶道具として使用されるも皿、鉢等にも多く使われている。 【鉄釉】 水打粘土、鬼板粘土を使用した鉄釉。貼花、印花を始め各種の装飾技法が発達した。 【志野】 長石のみを釉薬として使用したもの。美濃は鉄分の多い陶土長石を使用しているため、赤色の発色が見られるため通称赤志野と呼ばれて居り、赤津の長石は鉄分の含有率が少なく白色に発色するため、通称白志野と呼ばれている。 【織部】 一般的には、青織部のみを織部と称している。 黒織部は鉄釉に含めている。赤織部は赤い地土に白土にて文様を画き、鉄絵をあしらう。 絵織部は織部文様のみをあしらい、灰白釉で焼成したもの。 【古瀬戸】 鉄釉の一種で黒色の中に茶褐色の部分がある釉薬 【御深井】 安南呉須絵を絵付けしたもので還元焼成したものを御深井と称し、酸化焼成したものを安南、もしくは安南手と称している釉薬そのものは灰釉の一種で出現は平安前期である。 |
| 歴史 | 伝統工芸品に指定された七色の釉薬は、平安時代の灰釉に始まり、へら彫り、印花による華やかな文様によって花開き、鎌倉期、鉄釉、古瀬戸釉の出現により、貼付け、浮彫り等の装飾技法に一段とみがきがかかり、世にいう古瀬戸黄金時代となりました。
桃山期茶華道の発達に伴い、黄瀬戸、志野、織部の各釉が出現し、その優雅な美しさは、茶陶を中心として各焼物に及び、今日も変らず赤津焼の代表的なうわぐすりとして多く用いられています。 江戸時代の初期尾張徳川家による尾州御庭焼によって御深井釉が用いられ、玄人好みのうわぐすりが一段と冴えて、見事なろくろ技術や、たたら技術によって他に類をみない多彩さを誇り、十二種もの装飾を駆使して今日も尚、赤津焼に生かして、その伝統を守り制作されています。 後継者の育成も活発化し、「土ねり三年、ろくろ十年」といわれる伝統的技術の継承に二世らが情熱を燃やしており、赤津焼は今後も暮らしの伴侶として生き続けることでしょう。 |
◆展示場所
赤津焼会館
午前9時~午後5時 (昼休み:午後0時~午後1時)
休館日 祝祭日、第2・4土曜日
〒489-0022 愛知県瀬戸市赤津町94-4
TEL&FAX : 0561-21-6508
◆イベント開催
赤津焼祭り
期間:4月第3(土)・(日) 午前8:30~午後5:00/毎年開催
場所:赤津焼会館
内容:赤津焼廉売市 / 伝統工芸士作品展 / 伝統工芸士作品頒布会
せともの祭協賛 赤津焼祭り
日時:9月第2(土)・(日) 午前8:30~午後5:00/毎年開催
場所:赤津焼会館
内容:赤津焼廉売市 / 赤津焼作品展 / 伝統工芸士作品頒布会 / 庭茶会







