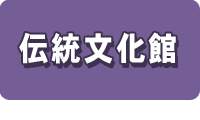

総数:127件
- 郷土芸能・民俗芸能 (55)
- 剣舞
- 吉和太鼓踊り
- 西馬音内盆踊り
- チャンチャコ踊り
- ちんどん屋
- 稲荷神社獅子舞
- 幸若舞
- 鬼来迎
- 寒水の掛踊
- 塩原の大山供養田植
- 綾子踊
- 天津司舞
- 無生野の大念仏
- 周防猿まわし
- 奥能登のあえのこと
- 能登のアマメハギ
- 能生白山神社舞楽
- 壬生の花田植
- 熊襲踊り
- アイヌ古式舞踊
- 麒麟獅子舞
- 鹿嶋神社稚児舞
- 諏訪神社獅子舞
- 大日堂舞楽
- 養父のネッテイ相撲
- 三河万歳
- 大宮踊
- 綾渡の夜念仏と盆踊
- 荒踊(三ヶ所神社例大祭)
- 郡上踊
- 江差追分
- 鶴崎踊
- 題目立
- はなとりおどり(増田地区)
- 真家みたまおどり
- 龍ケ崎の撞舞
- 泣き相撲
- 乙父のおひながゆ
- 青海の竹のからかい
- 竹富島の種子取祭
- おどり花見
- 加賀万歳
- 八戸えんぶり
- 白石踊(しらいしおどり)
- 唐戸山神事相撲 (からとやましんじずもう)
- 安芸のはやし田 (新庄のはやし田)
- 尾張の虫送り(祖父江の虫送り)
- 川俣の元服式
- 滝宮の念仏踊
- 西祖谷の神代踊
- 新野の盆踊り
- 和合の念仏踊り
- 花園の御田舞
- 花園の仏の舞
- 朝日豊年太鼓踊
- 祭り (33)
- 能・狂言 (2)
- 民俗技術 (4)
- 文楽(人形浄瑠璃)・人形芝居 (9)
- 神話・民話 (2)
- 暦 (1)
- 神事・儀式 (9)
- 歌舞伎 (4)
- 神楽 (7)
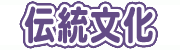
 |
|
《特徴》
みやま市瀬高町大江に伝わる幸若舞は、公式には「大頭流幸若舞」と言い、今日に伝存する唯一の幸若舞として、日本芸能史の上でも極めて高く評価されており、国指定重要無形民俗文化財となっています。
藩政時代(江戸時代)には毎年正月21日、柳河藩主の鎧の祝に、国家安全・武運長久を祈って、大江天満神社の神前でこの舞を演じていました。慶応2年(1866)からはその前日に繰り上げられ、現在の1月20日に奉納することが恒例になったといいます。
幸若舞は室町初期の頃、武士道鼓吹の舞曲として始まり、足利時代より信長、秀吉をはじめ、徳川幕府の初期まで幾多の武将に愛好され、また諸国大名によって奨励されたため、大いに隆盛を決めました。徳川の末期より、時代の流れ、趣味の変化、能曲、俗歌が盛んになるにつれて次第に衰え、その発祥地の福井県越前町でも後を絶ちましたが、福岡県みやま市瀬高町大江に「大江のめえ」とよばれて昔の姿をそのまま伝えています。
大頭流の舞曲は全部で42番あり平家物語、源平盛衰記、義経記、曽我物語などが題材とされています。現在まで舞われるものは日本記、浜出、扇の的、夜討曽我、安宅、八島、和泉城、高館の8曲です。平成20年より「敦盛」が復元され演じられました。
毎年1月20日に五穀豊穣を祈って大江天満宮の舞堂において奉納上演されます。
国重要無形民俗文化財
みやま市 コンテンツ内
「幸若舞」より転載
みやま市瀬高町大江に伝わる幸若舞は、公式には「大頭流幸若舞」と言い、今日に伝存する唯一の幸若舞として、日本芸能史の上でも極めて高く評価されており、国指定重要無形民俗文化財となっています。
藩政時代(江戸時代)には毎年正月21日、柳河藩主の鎧の祝に、国家安全・武運長久を祈って、大江天満神社の神前でこの舞を演じていました。慶応2年(1866)からはその前日に繰り上げられ、現在の1月20日に奉納することが恒例になったといいます。
幸若舞は室町初期の頃、武士道鼓吹の舞曲として始まり、足利時代より信長、秀吉をはじめ、徳川幕府の初期まで幾多の武将に愛好され、また諸国大名によって奨励されたため、大いに隆盛を決めました。徳川の末期より、時代の流れ、趣味の変化、能曲、俗歌が盛んになるにつれて次第に衰え、その発祥地の福井県越前町でも後を絶ちましたが、福岡県みやま市瀬高町大江に「大江のめえ」とよばれて昔の姿をそのまま伝えています。
大頭流の舞曲は全部で42番あり平家物語、源平盛衰記、義経記、曽我物語などが題材とされています。現在まで舞われるものは日本記、浜出、扇の的、夜討曽我、安宅、八島、和泉城、高館の8曲です。平成20年より「敦盛」が復元され演じられました。
毎年1月20日に五穀豊穣を祈って大江天満宮の舞堂において奉納上演されます。
国重要無形民俗文化財
みやま市 コンテンツ内
「幸若舞」より転載
| 所在地 | 福岡県みやま市 |
|---|---|
| 展示場&開催場所 | 大江天満宮境内舞堂 |
| 問い合わせ先 | みやま市商工観光課 |
| アクセス | JR鹿児島本線瀬高駅から車で約5分
九州自動車道みやま柳川I.C.から車で約5分 |
| 観るポイント | 平成20年に復元された「敦盛」は、あの織田信長が舞ったとされています。「人間五十年」から始まる一節は一度は聞いたことがあるかと思います。 |







