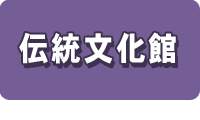

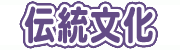
 |
|
 《特徴》
《特徴》左義長まつりは近江八幡に春の訪れを告げるお祭りで、織田信長も盛大に行い、自ら華美な衣装で踊り出たと伝えられています。
織田信長亡き後、八幡城下に移住してきた人々は、既に4月に行われていた八幡まつりに参加を申し入れましたが、松明の奉火場所が無く、また新参とのことで断られたため、これに対して、安土で行われていた左義長まつりを始めたことが起源とされているとも伝えられています。
左義長はその年の干支に因んだ物を主としテーマを決めて作成されます。
松明、ダシ、十二月(赤紙)の3つの部分を一本(基)にし、前後に棒を通し、つり縄で括り固め御輿のように担ぐように作り上げます(これ全体を左義長と呼びます)。前方となる正面に「だし」と呼ぶ作り物は意匠を凝らしたものとなっています。
干支の作り物を「むし」と呼び、背景は円形、方形、扇形など「台」と呼ぶ部分を作り取り付けます。この素材が、穀物「大豆、黒豆、小豆、胡麻等)や海産物(鰹節、昆布、するめ、干魚等)の食物を使って、その素材の色を活かして作り上げることが大きな特徴です。
左義長の担い手は踊子(おどりこ)と呼ばれ、その服装は、揃いの半纏を羽織る姿が一般的です。近年は少数になりつつありますが、女物の長襦袢を着用したり、化粧をするなど、変装した格好で左義長まつりへ参加するものも少なくはありませんでした。
これには、諸説ありますが、織田信長が自らの正体を隠すために派手な出で立ちで参加したとの話を、近世の人々が変装するものと解釈したのではないかと言われています。
左義長を担ぐ人々は口々に「チョウヤレ・チョウヤレ」と「マッセ・マッセ」と声を発しています。前者は「左義長さしあげ」後者は「左義長めしませ」からこのような掛け声になったものと思われます。
[国選択無形民俗文化財]
社団法人 近江八幡観光物産協会 コンテンツ内
「左義長まつり」より転載
| 所在地 | 〒523-0828 滋賀県近江八幡市宮内町257 (日牟禮八幡宮) |
|---|---|
| 展示場&開催場所 | 日牟禮八幡宮及びその周辺 |
| 問い合わせ先 | 社団法人 近江八幡観光物産協会 |
| アクセス | 名神高速道「竜王」インターより15km
お祭り開催時にはシャトルバスが出ております。 詳細は協会様HPをご参照ください。 |
| 観るポイント | 左義長が旧城下町を中心に自由に練り歩いて行われる「組合せ」(左義長のけんか)や、祭の最後に日牟禮八幡宮で行われる左義長奉火がみどころの一つとなっています。
また、経費を惜しまず各町の誇りをかけて制作された「ダシ」と、日牟禮八幡宮境内で行われる左義長ダシコンクールもポイントです。 |
| URL | https://www.omi8.com/omihachiman/festival/sagicho/ |







