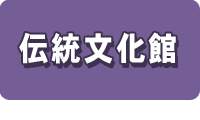

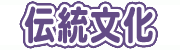
 |
|
 《特徴》
《特徴》[ちんどん屋の元祖]
1845年(弘化02年)、千日前の大阪法善寺の飴売り、飴勝は、竹製の鳴り物と売り声で人気者になった。 この売り声を売ることが出来ないかと考えた飴勝は、寄席の客寄せを請け負う。短い法被に大きな笠脚袢にわらじ、拍子木をさげて町にで、「今日は松屋町の何々亭…」とやった。
これがちんどん屋の元祖といわれている。
[東西屋・広目屋の誕生]
飴勝の仕事を引き継いだ勇亀は、芝居の口上をまねて「東西、トーザイ」と大声で叫びつつ、町中を触れ回った。このため勇亀は『東西屋』と呼ばれる。以後路上広告業は、「東西屋」に。
大阪出身の東西屋、秋田柳吉が初めて東京で、東西屋式の宣伝を行った。秋田は広目屋と名乗り、東西屋の拍子、口上に、さらに軍楽隊をプラスし、楽隊広告を誕生させた。彼のまねをする業者が増え、宣伝行列のことを広目屋というようになった。
[ちんどん屋の始まり]
大正時代に考案された「ちんどん太鼓」。ひとりでいろんな楽器を演奏できるよう鉦と太鼓を一緒にしたものだが、ここから東西屋、広目屋は「ちんどん屋」と呼ばれだした。
また、この頃映画のトーキー化により職を奪われた楽士達が、技術を生かせるちんどん屋に入ってきた。サーカスの楽士、寄席の芸人、大道芸人や物売り、ただの声の大きい人、夜逃げしてきた人なども同居するようになった。
[第二次世界大戦と戦後のちんどん屋]
1941年(昭和16年)、第二次世界大戦に伴い大道芸が一切禁止。ちんどん屋が浮かれて町を歩く時代ではなくなった。また、昭和30年代後半からテレビが普及。大衆の音楽の好みの変化もあり、ちんどん屋は古くさいといわれるようになる。
[ちんどん屋のビジネス展開]
現ちんどん通信社代表・林幸治郎氏によって、ビジネスとしての「ちんどん屋」が展開される。
【柔軟な対応力】を活かして、街頭宣伝やお祭り・イベント、海外公演等、多岐にわたるメディアで大活躍。
ちんどん通信社~(有)東西屋 コンテンツ内
「ちんどん屋の歴史」より転載(一部修正)
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
|---|---|
| 展示場&開催場所 | 様々な場所で活躍しておりますので、HPをご覧ください |
| 問い合わせ先 | ちんどん通信社~(有)東西屋 |
| 観るポイント | 参加イベントや活動につきましては、HPに詳細が掲載されております。 |
| URL | http://www.tozaiya.co.jp/ |





