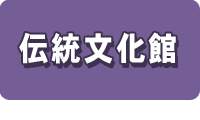

総数:127件
- 郷土芸能・民俗芸能 (55)
- 剣舞
- 吉和太鼓踊り
- 西馬音内盆踊り
- チャンチャコ踊り
- ちんどん屋
- 稲荷神社獅子舞
- 幸若舞
- 鬼来迎
- 寒水の掛踊
- 塩原の大山供養田植
- 綾子踊
- 天津司舞
- 無生野の大念仏
- 周防猿まわし
- 奥能登のあえのこと
- 能登のアマメハギ
- 能生白山神社舞楽
- 壬生の花田植
- 熊襲踊り
- アイヌ古式舞踊
- 麒麟獅子舞
- 鹿嶋神社稚児舞
- 諏訪神社獅子舞
- 大日堂舞楽
- 養父のネッテイ相撲
- 三河万歳
- 大宮踊
- 綾渡の夜念仏と盆踊
- 荒踊(三ヶ所神社例大祭)
- 郡上踊
- 江差追分
- 鶴崎踊
- 題目立
- はなとりおどり(増田地区)
- 真家みたまおどり
- 龍ケ崎の撞舞
- 泣き相撲
- 乙父のおひながゆ
- 青海の竹のからかい
- 竹富島の種子取祭
- おどり花見
- 加賀万歳
- 八戸えんぶり
- 白石踊(しらいしおどり)
- 唐戸山神事相撲 (からとやましんじずもう)
- 安芸のはやし田 (新庄のはやし田)
- 尾張の虫送り(祖父江の虫送り)
- 川俣の元服式
- 滝宮の念仏踊
- 西祖谷の神代踊
- 新野の盆踊り
- 和合の念仏踊り
- 花園の御田舞
- 花園の仏の舞
- 朝日豊年太鼓踊
- 祭り (33)
- 能・狂言 (2)
- 民俗技術 (4)
- 文楽(人形浄瑠璃)・人形芝居 (9)
- 神話・民話 (2)
- 暦 (1)
- 神事・儀式 (9)
- 歌舞伎 (4)
- 神楽 (7)
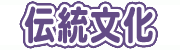
 |
|
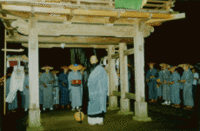 《特徴》
《特徴》夜念仏は、新仏(1年のうちに亡くなった人)のある家を回り、その霊を慰めるために、回向(えこう)を手向け、余興として手踊り(盆踊)を踊る盆の行事です。かつては、三河山間部から岐阜県の恵那市(山岡、串原、上矢作)にかけて広く行われ、足助地区でも葛沢町や切山町など14地区(17の村)で行われていましたが、今も伝わるのは、この綾渡の里だけです。
月明かりの中、静かに念仏を唱和する声が、鉦(かね)の音とともに高く、あるいは低く、田面をなぜる涼しい風に乗って流れてきます。星空をながめながら、無心にこの称名(しょうみょう)の声に聞き入ると、人生の無常感というか、哀愁というか、ことばで言いあらわせない境地に引き込まれてゆきます。綾度の夜念仏は、民俗芸能という呼び名はふさわしくなく、人々の仏に対する祈りそのものなのです。
昔、夜念仏は、若連中(35歳までの青年)の盆の行事で、昔は旧暦の7月1日から17日まで行っていました。1日は『地獄の口開け』で練習開始日、10日は平勝寺の施餓鬼供養、13・14日は新仏のある家を回り、15日は他村へ、17日は平勝寺の観音供養でした。
現在は、青年の数が少なくなり、若連中では継続ができなくなったので、昭和35年に保存会を結成しました。そして、新仏のある家を回ることもなくなり、今では8月10日と15日の2回、平勝寺境内で行っています。午後7時頃に平勝寺の参道の幟立てに集合して隊列を組み、『道音頭』を唱えながら、石仏の前で『辻回向』、山門前で『門開き』、観音堂前で『観音様回向』、氏神神明宮前で『神回向』、最後に平勝寺本道前で『仏回向』を唱えて終わります。
盆踊りは、楽器を使わず、『音頭とり』の歌う唄に合わせて下駄の足拍子だけで踊る、素朴な踊りです。今は音頭とりが踊りの輪の外に出て歌いますが、昔は特定の音頭とりはなく踊り子の中で歌に自信のある人が、踊りながら歌ったといわれます。越後甚句・御岳扇子踊り・高い山・娘づくし・東京踊り・ヨサコイ・十六踊り・御岳手踊り・笠づくし・甚句踊り(足助綾度踊り)の10曲の唄が伝えられていますが、扇子を使う踊りと使わない踊りがあります。昭和20年代の終わり頃から女の人や子供達も参加するようになり、今では老若男女が輪になって踊ります。
[ユネスコ無形文化遺産(風流踊)] [国指定重要無形民俗文化財]
提供:足助観光協会 様
| 所在地 | 愛知県豊田市綾渡町(旧足助町)・平勝寺境内 |
|---|---|
| 展示場&開催場所 | 愛知県豊田市綾渡町(旧足助町)・平勝寺境内
毎年:8月10日、8月15日 |
| 問い合わせ先 | 豊田市「綾渡の夜念仏と盆踊」保存活用推進協議会事務局 豊田市文化財課
Tel 0565-32-6561/Fax 0565-34-0095(定休日:土日祝、12/29~1/3) |
| 伝統文化の 体験・一般参加 |
【見学】
綾渡夜念仏と盆踊を見学いただけますが駐車場がないため、事前予約にてバスにてお願いいたします。 ※詳細は豊田市文化財課へ 場所:愛知県豊田市綾渡町(旧足助町)・平勝寺境内 日時:午後7時頃から 毎年8月10日、8月15日 |
| URL | http://asuke.info/event/aug/entry-700.html |







