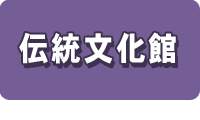

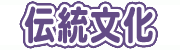
 |
|
 《特徴》
《特徴》春鍬祭はその年の豊作を予祝して行う田遊びの神事で、毎年2月11日に樋越神明宮で行われます。
寛政10年(1798)にはすでに行われていたようで、神明宮の氏子の、原、森下、上樋越、中樋越上、中樋越下、下藤川の6つの地区から、禰宜、作頭、鍬持などの諸役が出て、神明宮の拝殿で祭典が行われた後、拝殿の前に竹を4本立てて注連縄を張った祭場を作ります。
その地を田に見立て、榊や樫の枝に餅をつけて鍬に見立てたものを持った「鍬持(くわもち)」が拝殿の前でくろぬりの仕草などをし、祭典長の禰宜(ねぎ)が頃合いを見て「春鍬よーし」と叫ぶと、一同が「いつも、いつも、もも世よーし」と唱和し、その年の豊作や無病息災が祈願されます。
これを3回繰り返すと、持っていた鍬を投げ、観衆が鍬を奪い合います。とった鍬を家に飾っておくと、養蚕があたり、また、一緒にまかれた稲穂のついたままの初穂を拾った人の家は、豊作間違いなしといわれています。
国重要無形民俗文化財
玉村町サイト コンテンツ内
「春鍬祭」より転載
| 所在地 | 群馬県佐波郡玉村町 |
|---|---|
| 展示場&開催場所 | 樋越神明宮 |
| 問い合わせ先 | 玉村町教育委員会生涯学習課文化財係 |
| 観るポイント | 祭典長の禰宜(ねぎ)が祭事に使っていた鍬の奪いあいは、観ている人たちが参加できます。皆で一体となって行事を盛り上げているところが観るポイントです。 |







